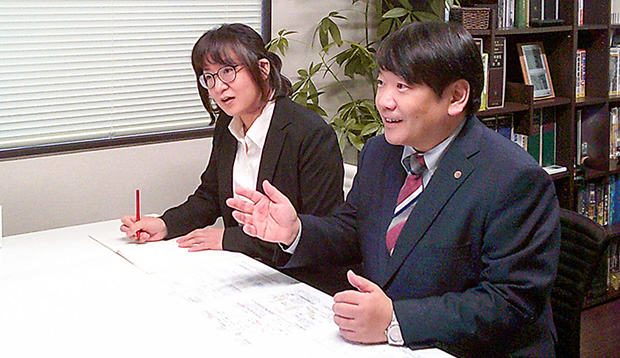こちらでは、相続税の計算についてご説明いたします。
相続税とは、ご家族が亡くなり相続が発生したことを受け、「相続や遺贈により財産を取得した者」に課せられる税金のことをいいます。
相続税は、税金を納める方がご自身で相続税の納税額を算出し納税までを行う「申告納税制度」を採用しているため、相続人自らが課税対象となる財産を見分けて評価、計算を行わなければなりません。
しかしながら、相続税の計算は相続税に関する知識を持ち合わせていないと正確な納税額を算出することができないだけでなく、さまざまな控除や特例を、財産評価や相続税の計算過程において適所で用いて、正確な納税額を算出しなければなりません。
なお、控除や特例を適用した結果、相続税額が0円となった場合でも、その旨について申告しなければ適応できないため注意しましょう。申告期限までに遺産分割がまとまらない場合には、法定相続分で相続したことにして相続税を申告、納税します。
申告期限後、遺産分割がまとまった場合、更正の請求や修正申告を行います。
納税額の算出の仕方について
相続税には「基礎控除額」が設定されており、相続税の課税対象となる財産総額のうち、基礎控除額を超えた部分にのみ相続税が課されます。
算出の結果、相続税の課税対象となる財産総額が基礎控除額を下回る場合には納税義務は生じません。
- 〈基礎控除額〉相続税の基礎控除 = 3000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
- 〈遺産総額(正味の遺産額)〉プラスの財産-マイナスの財産・非課税財産+暦年課税の持ち戻し分
- 〈課税遺産総額〉 遺産総額(正味の遺産額) - 基礎控除額
- 〈各相続人等の税額〉課税遺産総額 × 各人の取得割合 × 税率 - 控除額
遺産総額(正味の遺産額)を算出する際には、まず被相続人のプラスの財産から借金等のマイナスの財産や非課税財産を差し引いた金額に、相続開始前3年間になされた暦年贈与分を持ち戻して計算しなければなりません。この、暦年贈与の持ち戻し期間は、令和6年から徐々に拡大され、最終的に7年間が持ち戻しの対象となるとされていますので注意が必要です。
申告内容が間違っていたり、申告漏れをしたりすると、延滞税や過少申告加算税などといったペナルティが課せられる恐れがありますので、大切な財産を無駄に減らすことのないよう、相続が発生したら早急に相続税申告の有無を確認して手続きに取り掛かり、期限内に申告納税まで済ませましょう。
相続税申告は、相続税の知識と経験豊富な専門家に依頼し、円滑かつ正確な相続税申告を行いましょう。みんなの相続遺言相談プラザ長崎では、税理士の独占業務は、提携先の税理士と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。