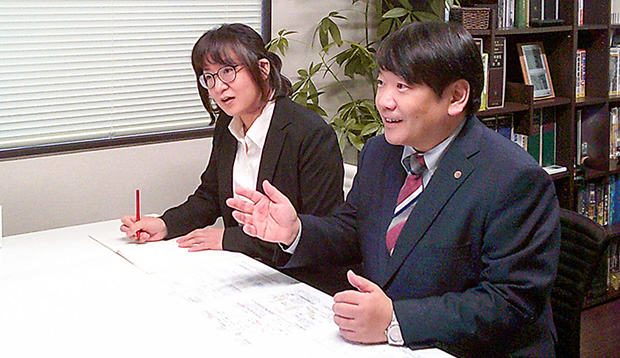寄与分の制度とは亡くなった人の療養看護に努めたり、被相続人の事業の手伝いを行ったりなどして、被相続人の所有する財産の維持や増加に貢献をした相続人に対して、その他の相続人との間の不公平をなくすために設けられた制度です。
寄与分は、相続人同士で行う遺産分割協議で主張するところから始まります。
寄与分の主張が認められると相続財産の分割割合に影響するため、他の相続人の取り分けが少なくなるため、主張を反対される可能性もあります。
そのため、寄与分の主張を考えている場合は、事前にご自身が寄与分を主張できる事例に当てはまっているのか十分に確認することが必要です。他の相続人とトラブルにならないためにも、相続人全員が納得できる主張になるよう注意しましょう。
では、どのようなケースで寄与分が認められるか説明していきます。
寄与分が認められる事例
寄与分は下記のように相続人に対する財産維持、増加に貢献した人がその貢献度に応じて受け取ることが出来ます。
例
- 「金銭等出資型」 被相続人に生活費・医療費等を渡し、財産の維持や増加に貢献した。
- 「看護療養型」 被相続人の療養看護に努め、財産の維持や増加に貢献した。
- 「家業従事型」 被相続人が営なむ事業に従事し、財産の維持や増加に貢献した。
なお、ケースによって寄与分が認められるかどうか、認められるとしてどの程度受け取れるのかが異なります。ご自身での判断が難しい場合は専門家にご相談されることをおすすめいたします。