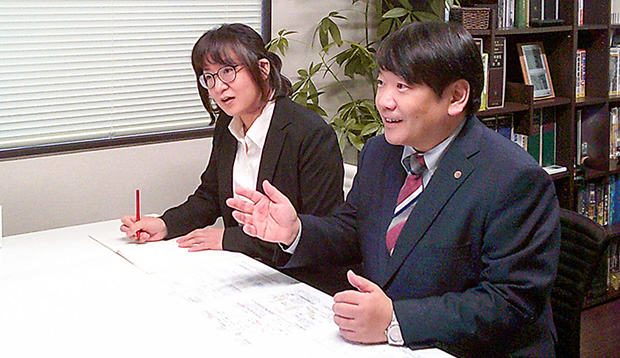相続によって取得した預貯金や株などの金融資産は、自動的に解約あるいは名義変更されるものではなく、取得した方がご自身で手続きする必要があります。こちらのページでは相続財産である預金と株式の手続きについてご説明いたします。
預金の手続き
口座の名義人が死亡した場合、銀行に名義人死亡の旨を連絡します。複数の銀行と取引がある場合はすべての銀行にそれぞれ連絡する必要があります。
銀行が名義人死亡の連絡を受けると、その口座は凍結され、相続手続きを終え凍結解除の手続きを行わない限り原則として預金の引き出しはできなくなります。
口座凍結前に済ませておくこと
口座凍結後はATMでの残高照会や通帳記入もできなくなるため、銀行へ連絡する前にあらかじめ記帳しておくほか、公共料金の引き落とし口座となっている場合は請求先の変更を済ませておくとよいでしょう。
口座凍結前の預金引き出しには注意
口座が凍結される前に、被相続人の口座から預金を引き出しておきたいとお思いになるかもしれません。しかし凍結前に預金を引き出し被相続人の財産を消費してしまうと、相続放棄ができなくなります。また相続人同士のトラブルの原因になるなど、リスクが高いと考えられますのでご注意ください。
それでも、医療費や葬儀費用の支払いや当面の生活費のためにどうしても預金を引き出したいということもあるでしょう。その場合は仮払い制度を利用し凍結口座から預金の払い戻しを受けることも可能です。この制度を利用すると、自己の法定相続分の1/3の金額を、遺産分割することなく受け取ることができます(ただし、1つの金融機関で払い戻せる金額の上限は150万円)。
口座凍結解除の方法
口座の凍結を解除するために、必要書類を揃えて銀行へ提出し、口座の解約あるいは口座名義人の変更手続きを行います。遺言書の有無などご状況によって必要となる書類は異なるので事前に確認しておきましょう。
遺言書がある場合
- 相続届
- 遺言書(自宅等で保管していた自筆証書遺言の場合は、検認済証明書も必要)
- 被相続人の戸籍謄本(死亡が記載されたもの)
- 相続人の戸籍謄本
- 相続人の印鑑登録証明書
- 通帳 など
遺言書はないが遺産分割協議書がある場合
- 相続届
- 遺産分割協議書
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)
- 相続人の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 通帳 など
- 上記は一例で、銀行ごとに必要書類は異なる可能性があります。詳しくは各銀行へお問い合わせください。
株式の手続き
相続財産の中に株式が含まれている場合は、株式移管の手続きを行います。手続き方法はその株式が上場株式か非上場株式かによって異なります。
上場株式の場合
原則、証券会社に対して相続手続きを行います。ただし端株等がある場合には、その株式の株主名簿管理人である信託銀行に対しても相続手続きを行う必要があります。手続きが複雑であるため、一度専門家に確認するとよいでしょう。
証券会社での手続き
証券会社では顧客ごとに取引口座を開設しているので、その口座で保有していた株式を相続人の口座へ移管します。この時必要となる書類は証券会社によって多少異なりますが、主に以下の書類を揃えて提出します。
- 証券会社所定の同意書(相続人全員分)、引継ぎ用紙
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑登録証明書
非上場株式の場合
株式を発行している会社での手続きが必要です。手続き方法は会社ごとに異なりますので、それぞれの会社にご確認ください。