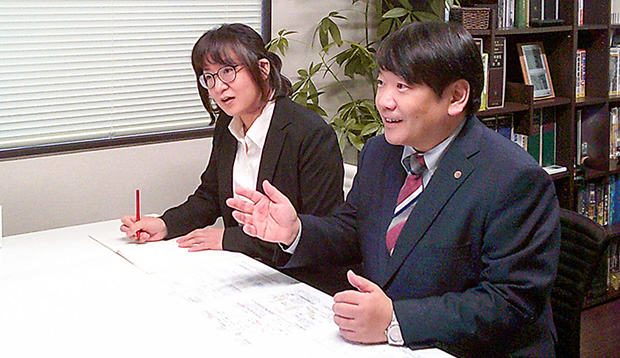相続税には、被相続人から相続した財産のうち、一定の金額までは相続税がかからない非課税枠が設定されています。これを「基礎控除」といい、遺産総額が基礎控除額を下回る場合は、相続税がかかることはありません。
基礎控除額は、以下の計算式で算出することができます。
相続税の基礎控除額=3,000万円 +600万円×法定相続人の数
遺産総額の計算方法
まず、相続税額を計算するうえで必要となる遺産総額について確認しましょう。
相続人の遺産にはプラスの財産(金融資産、不動産等)のほかに、マイナスの財産(借金、住宅ローン等)も含まれている場合があります。相続税における遺産総額は、プラスの財産からマイナスの財産を差し引いた金額となります。
遺産総額=プラスの財産-マイナスの財産
基礎控除の算出に必要な法定相続人とは
法定相続人とは、民法で定められた遺産を相続する権利を有する人のことを指します。相続の際、常に法定相続人となるのは配偶者です。そしてその他の親族については、以下の相続順位に応じて法定相続人となります。
相続人の相続順位
- 第1位:被相続人の子(直系卑属)
- 第2位:被相続人の父母(直系尊属)
- 第3位:被相続人の兄弟姉妹
上位の順位の人が存在すれば、下位の順位の人が法定相続人になることはありません。例えば被相続人に配偶者と子がいるのであれば、相続順位の第2位以下の人に相続権は発生せず、法定相続人は配偶者と子のみとなります。
法定相続人の数え方の注意点
基礎控除額の計算式からわかるとおり、法定相続人の数が多くなればそのぶん基礎控除額も高くなります。しかしながら相続人に養子がいる場合や一部の相続人が相続放棄をした場合は、法定相続人の数え方に注意が必要です。
養子は人数に制限がある
法定相続人を増やす方法に、養子縁組があります。被相続人に養子がいた場合は、その養子も相続権を持ち基礎控除額を増やすことができるため、相続税対策として有効な手段といえます。
ただし、基礎控除額の計算に含めることのできる養子の数には制限が設けられています。数多くの養子を迎えたとしても、上限を超えている場合は相続税対策にはならないためご注意ください。
法定相続人の数に含めることのできる養子の数
- 被相続人に実子がいる:養子の数は1人が上限
- 被相続人に実子がいない:養子の数は2人が上限
相続放棄した相続人も数に含めることができる
相続放棄した相続人は、被相続人の財産や債務を一切継承することができません。しかしながら相続税においては、相続放棄をした相続人がいたとしても、その放棄はなかったものとして計算します。
たとえば法定相続人にあたる人物が3人いて、そのうちの1人が相続放棄をした場合、相続税の基礎控除額は法定相続人3人として計算します。つまり相続放棄をしたからといって、基礎控除額算出における法定相続人の数が減り、相続税額が増えることはないということです。
基礎控除以外の特例・控除
相続が発生した際、基礎控除はすべての人に適用されますが、そのほかにも相続税には控除や特例、軽減制度が設けられています。これらを適正に適用できれば、相続税額を抑えることにつながります。
小規模宅地等の特例
相続財産である不動産に、被相続人の家族が居住している場合や、事業所として働いている人がいる場合に、相続税が減額されるという制度です。それぞれのケースごとに適用要件が定められていますが、要件を満たし特例を適用できれば、土地の評価額は最大80%まで減額することができます。
配偶者の税額軽減(配偶者控除)
相続などによって被相続人の配偶者の取得した遺産額が、「法定相続分の相当額」あるいは「1億6,000万円」のどちらか多い方の金額を下回る場合、配偶者に対して相続税はかからないという制度です。
未成年者控除
法定相続人が未成年者の場合、相続開始時の年齢から成年(18歳)になるまでの年数に応じて、1年につき10万円の金額が納税額から控除されます。
障害者控除
障害者に対して設けられた制度で、一般障害者の場合は相続開始時の年齢から85歳になるまでの年数に応じて、一年につき10万円、特別障害者の場合は相続開始時の年齢から85歳になるまでの年数に応じて、一年につき20万円の金額が納税額から控除されます。
相続した遺産額が基礎控除額を下回る場合は相続税申告を行う必要はありません。それに対し、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減、未成年者控除、障害者控除などの適用によって相続税額が0円になった場合は、特例・控除を適用したことで納税がなくなった旨を申告する必要がありますのでご注意ください。
ご自身が相続税申告の対象となるのかわからない、特例や控除の適用について詳しく知りたいなど、長崎で相続税についてご不明点がある方は、みんなの相続遺言相談プラザ長崎までお気軽にお問い合わせください。みんなの相続遺言相談プラザ長崎では各士業と連携しワンストップで長崎の皆様をサポートいたします。